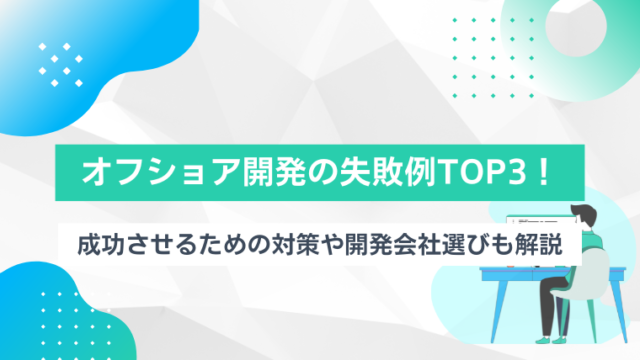グローバル開発体制が進むなか、海外チームとのオフショア開発でスクラム開発を取り入れる企業が増えています。しかし、時差や文化の違いによる運用の難しさに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、オフショア開発でもスクラム開発を機能させるための具体的な運用術や成功事例、チーム構築のポイントを解説します。海外チームとの開発でも「スクラムは使える」と実感できる内容になっています。
バナー-1-1.png)
なぜオフショア開発とスクラム開発は相性が良いのか?

ウォーターフォール型では限界がある理由
従来のオフショア開発では、ウォーターフォール型が主流でした。しかしこの手法では、初期設計から開発完了までに長い期間を要し、仕様変更に対して柔軟に対応できないという課題がありました。特に海外チームとの開発においては、距離や文化の違いが進捗や品質に影響を及ぼすことがあり、従来の一括請負型ではその限界が顕著になっています。
スクラム開発の柔軟性と改善性
スクラム開発は、短期間のスプリントを繰り返すアジャイル開発手法のひとつです。定期的な見直しと調整を重ねるため、要件の変更や優先順位の入れ替えに柔軟に対応できます。これは、時間差や仕様の誤解が起きやすいオフショア開発において、大きな強みとなります。
オフショアチームがスクラムに向いている背景
近年では、アジア圏を中心にスクラム開発に精通したエンジニアが増えており、国際的な認定資格を有する人材も多数います。フィリピンやベトナムのエンジニアは、英語力とスキルの両面で実務に対応でき、スクラムマスターやプロダクトオーナーとの連携にも適応しやすくなっています。これにより、構築フェーズにおける支援の質が向上し、スクラム導入の成功率が高まっています。
オフショアでスクラム開発を機能させる構築ポイント

要件の明文化と共有ルールの整備
オフショア開発でスクラムを運用するうえでまず重要なのが、要件定義の明文化です。あいまいな指示やニュアンスの違いが手戻りの原因となり、開発効率を下げてしまいます。そのため、日本側が作成する仕様書や画面遷移図などの資料は、視覚的で具体性があり、誰が読んでも意図が伝わるように構築する必要があります。
さらに、定例会議のルールやドキュメントの管理方法なども含め、開発チーム全体で共有する運用ルールを最初に決めておくことで、スクラム開発における不整合の発生を防ぐ支援体制が整います。
ブリッジSEを活用したチーム設計
オフショアチームと日本側を橋渡しする役割を担うのが、ブリッジSEです。仕様の理解やタスク管理だけでなく、文化・言語の違いによる認識ズレを防ぐ役割も果たします。スクラム開発の中心にブリッジSEを配置することで、双方向の意思疎通を支援し、チーム全体のパフォーマンスを高めることが可能です。
特に、1日1回のデイリースクラムでは、日本語での整理→英語での展開が即時に行えるブリッジSEの存在が、進行のスムーズさを左右します。
ブリッジSEの具体的な仕事内容や求められるスキルについては、【ブリッジSEとは?オフショア開発の仕事や必要なスキルを解説 】もあわせてご覧ください。
スクラムマスターとPOの配置バランス
スクラムチームには開発チームだけでなく、スクラムマスターとプロダクトオーナー(PO)の存在が不可欠です。特にオフショア開発では、POが開発意図を伝える「翻訳者」としての役割を果たすことが求められます。
日本側でスクラムマスターとPOを兼任する場合は、現地チームの業務負荷や文化的背景を理解した進行が必要です。逆に、現地にもサブPOやリードエンジニアを配置することで、より自律的で分散的なスクラム開発体制の構築が実現できます。
バナー-1-1.png)
時差・文化・言語の壁を超えるための運用術

コアタイムを軸としたスプリントスケジュール
オフショア開発でのスクラム運用では、時差の影響をどう克服するかが大きな課題です。日本とフィリピン・ベトナムなどアジア圏との時差は1〜2時間と比較的小さいため、日中の「重なり時間(=コアタイム)」を意識したスケジュール構築が現実的です。
例えば、日本時間10時〜16時をコアタイムとし、この間にデイリースクラムやレビューを実施することでリアルタイムのやり取りを確保しつつ、それ以外の時間は各々で開発を進めるという運用が効果的です。
言語ギャップを埋める多言語マニュアルの整備
英語でのやりとりが前提となるオフショア開発ですが、曖昧な表現や文化的な言い回しは誤解のもとになります。そこで、日本語・英語の両言語で用意された設計ドキュメントや操作マニュアルの活用が重要です。仕様変更やバグ修正などの情報共有も、画像や図を交えた資料にすることで、言葉の壁を大きく低減できます。
スクラムの各イベント(スプリントプランニングやレビューなど)でも事前にアジェンダと用語の定義を明示しておくと、情報伝達の精度が格段に高まります。
異文化理解を前提としたプロセス設計
国によっては、指示を受けた内容をそのまま実行し、自らの判断で改善提案をしにくい文化背景があります。そのため、「なぜそのタスクを実行するのか」という目的共有と、柔軟な意思決定の許容度を高めたプロセス設計が求められます。
具体的には、スプリントの初期段階でプロダクトビジョンを共有し、単なるタスクの割り振りではなく、「顧客価値」を意識した開発姿勢を全体で育てることが効果的です。
定例ミーティングと非同期コミュニケーションの使い分け
すべてをオンライン会議でカバーしようとすると、時差や工数の負担が増えがちです。そこで、定例ミーティングは週2〜3回に絞り、それ以外はSlackやNotionなどのツールを活用するハイブリッド型の運用が有効です。
文面でのやり取りでは、発言履歴が残るため後追い確認も可能になり、情報伝達の透明性も高まります。これにより、時間を効率的に使いながら、スクラムの原則である「自己組織化されたチーム」の運用が可能になります。
オフショア開発×スクラムの成功パターン

スモールスタートでスプリントの精度を高めたケース
ある企業では、3名から始まる小規模なオフショア開発チームにスクラムを導入しました。最初の1〜2スプリントは試行錯誤があったものの、スプリントレビューとレトロスペクティブを通じて改善サイクルが機能し、3ヶ月後には中規模案件を無理なく回せる体制に成長しました。
このケースでは、当初からブリッジSEを配置し、細かな仕様の認識違いをその場で調整したことが成功の鍵となりました。
時差を活かした24時間開発フローの構築
日本と海外の開発チームが時間帯をずらしてタスクを継続的に処理する「24時間スプリント運用」を実現した例もあります。日中に日本側でレビューを実施し、夜間はオフショアチームが開発・修正を行うという循環により、通常より30%短い納期でのリリースが可能となりました。
ここでも、課題管理ツール(Jiraなど)とマニュアルの多言語化が、非同期コミュニケーションの支援に大きく貢献しています。
品質向上を重視した「ブリッジSE主導型」運用
品質を重視したあるプロジェクトでは、ブリッジSEがコードレビューや進捗管理にも関与し、日本側PMと連携しながら開発をリードしました。単なる連絡係ではなく、技術的判断やリスク検知も担う体制を構築したことで、バグ発生率が大幅に減少し、保守性の高いプロダクトが完成しました。
ブリッジSEの活用については、【ブリッジSEとは?オフショア開発の仕事や必要なスキルを解説】もあわせてご覧ください。
まとめ:海外スクラムは設計と運用次第で大きな武器になる
オフショア開発においても、スクラム開発は十分に機能します。ただし、その効果を最大化するには、チーム構築・運用設計・コミュニケーション支援の3要素をバランスよく整えることが不可欠です。
文化や言語、時差といった「障壁」は、丁寧なプロセスと役割設計によって「強みに変える」ことができます。ブリッジSEの活用や非同期ツールの工夫によって、日本と海外のチームが一体化し、自律的なスクラム運用が実現できます。
重要なのは、「国内と同じやり方をそのまま海外に押し付ける」のではなく、現地特性に合わせて柔軟に構築・改善していく姿勢です。信頼できるパートナーとともに設計・実行・改善を繰り返せば、オフショア開発におけるスクラムも、強力な武器になります。
もし貴社の開発プロジェクトにおいて、海外チームとのスクラム導入や運用支援にご興味があれば、お気軽にこちらのお問い合わせフォームよりご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適な体制をご提案いたします。
バナー-1-1.png)